今日はちょっと繊細な内容になるかもしれないので、微妙だなと思った時点で読むのをやめてください~。
人の生死に関するお話です。
先日、夫のおばあちゃんが亡くなった。
97歳、老衰という診断だった。
そこから私の頭のなかで色んな気持ちがわきでてきた。
今回はそんな私の頭のなかの過程をつらつらと書いていこうと思いマス。
みんな心の準備はしていた。
「もうそろそろ危ないかもしれない」
おばあちゃんは入院していたし、状態の変化もわかっていた。
私にもおばあちゃんとの思い出はある。数は少ないけど、楽しくお話していたなとか、そういった光景を思い出すと心が温かくなる。
孫の嫁なんだから、おばあちゃんからしたらそこまでの存在感だったんだろうなと思うんだけど。(悪い意味で言ってないです)
でも、おばあちゃんと話をするのは私も嬉しかった。私の祖父母はもうすでにこの世にいなかったから「おばあちゃんと話をしている」という事がすごくうれしかった。
最後の数年は施設に入っておられたし、ますます会う機会は少なくなってたんだけど。
でも「施設にはいはるんだ」と思ってる状態と「もういないんだ」と思うのとは全然違うんだなと思った。
やっぱり寂しいな。
私が思うんだから、私以外の夫や、おばあちゃんとの思い出がたくさんある人たちはもっといろんな事を考えるよね、と思うと心がキュッとなった。
つぎからつぎへと私の頭のなかのおしゃべりが始まる。
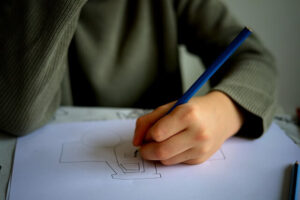
不安というか、心配というか、そういった感情が付いて回るから、心配性の左脳さんがしゃべっているんだろうか。
夫の心は大丈夫だろうか、苦しくないだろうか。
夫の気持ちを想像して、悲しくなる。
共感しているから悲しいのだろうか。同じ悲しみを感じようとしているからだろうか。
でも、もう少し、この気持ちに潜ってみる。
不安。心配。悲しい。寂しい。
そんなキーワードがでてくる。
でも、冷静に考えてみると私の感じている「不安」「心配」は一見「夫が悲しみで苦しくないか」の「心配、不安」なんだけど、
よくよく見つめてみたら、
そんな夫を見ている自分がつらいのかもな、と思った。そう思っている自分もいるなと思った。
その「心配、不安」には色んな意味がある。
夫を心配しているのも本当の気持ちだし、夫の悲しみ、喪失感に共感して悲しくなるのも本当の気持ちだ。
悲しそうな夫を見ている自分がつらいという気持ちも本当の気持ち。
別にだからなに?って感じなんだけど。
そうなんだけど、いろんな気持ちになっている自分がいるんだな、って再認識した。そういう自分をわかっていたかっただけだ。
深く考えなければ、夫の気持ちを想像して、共感しようとして、悲しくなって心配しているだけだと思いそうだけど。だけど「自分の事を考えて不安になっている」自分もいる。
そんな自分を否定するわけでもなく。
それが人間なんだよな、と静かに思う。
もっと極端にはっきりと、きつい言い方をすると「他人の心配をしているようで自分の心配をしている」という自分がいるんだな、という事を静かに受け入れる。

これに気づいて、じゃあどうするの?ってとこまでいこうとおもいます。
自分がしている心配、自分が感じている不安には何がある?と分解してみる。
そうすると、また、違う気持ちがわいてくるかもしれない。
物事の見え方がかわるかもしれない。
それに気が付くことが大切だ。
今回、私は、想像のなかで、悲しみいっぱいの夫をイメージして、そんな夫を見ているのは辛いな、と思った。
これも、分けて考えてみると、
夫の悲しみは夫の悲しみで、完全に夫の悲しみを知ることはできない。共感しようとする気持ちは大事だけど、なり切ることはできない。
そして、夫の悲しみを私がもらう事はできない。夫には夫の「心の回復時間」が必要。私ができる事はそれを静かに受け止めて「待つ」事だ。
「過剰な心配はお節介だ」ということも思い出さなければいけない。
そもそも「心配」という事をもう少し別角度で深く掘り下げてみると、一番奥には相手への「信頼度合い」が隠れていたりする。
相手が課題を乗り越えることができると信じていたら、本来はそこに「心配」はないはずだ。
「心配する」という事は、自分が心のどこかで「相手が乗り越える事ができないかもしれない」と思っている自分がいるかもしれないということに気が付くことができる。
じゃあなぜそう思うのか?と、そこからまた考えを深堀る事ができる。
そして、
もしかしたら、自分の思考グセがそう思うようになっているのかもしれない、と考える事もできる。自動思考でそう思うようになっていると、なかなか気づけない。だからこそ、自分の「思考の偏り」に気が付くことが大事だ。
無意識に「心配するクセ」が働いているのかもしれない。
自動思考でそうなっているならば、その思考回路に新たな回路を作って、そっちに電気を流さないといけない。それにはまず、自分が「気づく」ことだ。
「心配性」な人って、心の奥では「自分が傷つきたくない」という思いをもっていることもある。

じゃあ何で必要以上に「傷つくことを恐れてしまうのか?」とまた自分に潜ることができる。
人に裏切られた経験がある人は無意識に警戒心が強くなる。そういったことが「心配性」の要因になってることもある。
そこに気づけたら、「過去の自分の経験」と「今の出来事」は全く関係ないという事がわかるかもしれないし、「心配する必要はないのかも」と思えるかもしれない。
いろんな方法がある。
この「原因」を見つめる方法は「原因論」ベースの考え方で、もちろん「目的論」だけを使って、とにかく「自分はどうしたい?」と思うことも一つだ。
「不安になって心配している自分がいるな。でも、なんでだろう?」と掘り下げていく過程はすっ飛ばして、「自分はどうしたい?」「自分と相手の関係性はどんな感じがいい?」「自分にできる事って何があるっけ?」と目的論にそって考えていくのもありだ。
私はやっぱり、原因論で考えてる間は前に進めなくなったとしても、「でもなんで?」と考えるのがすきなので、やっぱりその過程をも大事にしたいな、と思ったりする。
目的論は素晴らしい考え方だけどね。
「人間にはこういう所もあるんだよね」って、いいとこも悪いこともすべてを認識して受け入れたいと思っている。
話はだいぶ逸れたけど(ゴメンナサイ)
今回、おばあちゃんの事をきっかけにまた、いろんな事が学びになった。
そう。寂しいけどね。本当に。
でも「死」をなんか悪いもの、怖いもの、って考えるから、余計に要らんことを考えるよなーと思ったりしてて、
「人間も自然の一部」と考えたり、ほかの「意味づけ」をすることで瞬間的にくる「感情」はかわってくるなとも今回おもった。
「お役目を全うして次のステージに進んだ」と思う事もできる。
そう思えたら、「悲しい」「寂しい」という気持ちはありつつも、また違うプラスの感情がわいてきたりもする。
「次のステージでも目一杯たのしんでね!」と思えるかもしれない。
まぁまだでも、私のなかでも、やっぱり「寂しい」気持ちが今は勝ってしまうけど。
どんなことがあっても、残された人間はやっぱりそれぞれの「この世でのお役目を全うする」ことが大事だ。
淡々と静かに、丁寧に、生きる。
難しく考えず、自分を大切にし、自分以外の人も大切にする。人間だけではなく、それ以外のすべての物も大切にする。
一生懸命生きる。
できる事を淡々と。
できる事が「ある」ことがありがたい。
「五感」を使って「感じれること」がありがたい。
色々脱線しましたが、思い浮んだことはほんまなので、隠すことなくそのままの「今」の私を書きました。
明日にはまたなにか変わっているかもしれないけど。
変化することもまた素晴らしい。
変化できることがありがたい。
日々、色んな経験を積み重ねている。
そこで、経験や学びを元にして「感情」の変化が起こることは普通の事だ。
「変化」もまた素晴らしい。
私の目的は「みんなの笑顔をみること、みんなの笑顔をみて私も微笑んでいる」状態だ。
その目的を常に胸に置いておいて、淡々と生きますよ。はい。
何があっても、何もなくても、ありがたい。
最後までお付き合いいただきありがとうございました!この後も素敵な時間をお過ごしください。ではまた~






コメント